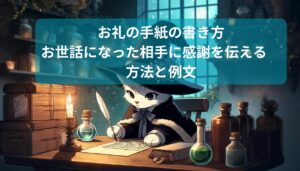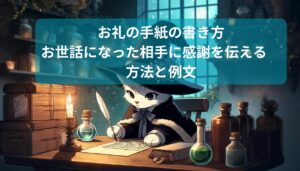頂き物をいただいた際に、感謝の気持ちを伝えるお礼状は、丁寧なマナーとして欠かせないものです。個人でお礼状を書く場合、どのような文面にすれば良いか迷うこともあるでしょう。本記事では、頂き物に対するお礼状の書き方と、すぐに使える例文を紹介します。お礼状を送るタイミングや手書きのポイント、相手に喜ばれる文例を通して、個人でも安心してお礼状を作成できるようサポートいたします。
- 個人で送る頂き物のお礼状の基本的な書き方とマナー
- 句読点を使わない理由や手書きの効果についての理解
- 各シーン別に適したお礼状の具体的な例文
- 遅れた場合のお詫びを含めたお礼状の対応方法
頂き物のお礼状 例文 個人向けの基本的な書き方

 アカネ
アカネわ…こんな丁寧に!でも…何てお礼を伝えれば…
よくある不安とその対処法





あの…“失礼にならない書き方”って、どこまで気にしたらいいんでしょう…?



大丈夫よ。“気持ちが伝わるか”を大切にすれば、完璧じゃなくても十分伝わるわ。
お礼状を書く際、「どのような言葉で感謝を伝えればいいのかわからない」「形式を間違えると失礼にならないか心配」といった不安を抱く方は少なくありません。そうした声に寄り添うことが、お礼状を書く第一歩につながります。
まず、「完璧な文章でなくても、気持ちを伝えることが大切」ということを理解しておきましょう。かしこまりすぎるよりも、相手との関係性に合った表現を心がけることが安心につながります。
例えば、目上の方に送る場合は敬語を意識しつつ、型通りすぎないように一文だけでも心を込めた一言を添えると良い印象になります。逆に親しい間柄であれば、丁寧語をベースにややくだけた表現でも失礼にはなりません。
また、文章の長さや構成に悩む方も多いですが、冒頭に感謝の気持ち、中盤で具体的な内容、最後に今後のお付き合いへの言葉という流れを意識すると、自然で読みやすいお礼状になります。
このように、「完璧」を目指すよりも「誠意ある対応」を意識することが、結果として最も伝わるお礼状になります。
手紙を書くときに気をつけたいNG例





あっ…これじゃカジュアルすぎ?



ちょっとね。でも、心を込めれば書き直せるわ。
お礼状で避けるべき表現やマナー違反を知っておくことは、相手に失礼のない丁寧な印象を与えるうえでとても重要です。
よくあるNG例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 感謝の言葉がない、または形式的すぎて心がこもっていない
- 相手の名前を間違えている(漢字や敬称のミスも含む)
- 句読点や記号を多用しすぎて軽い印象になる
- 長々と自分の話ばかりになっている
- 贈り物の感想がない、または適当な表現
例えば、「この前はどうも」という書き出しでは、丁寧さや誠意が十分に伝わりません。「このたびは、心温まる贈り物をありがとうございました」といった表現の方が好印象です。
また、形式を守ろうとするあまり、テンプレートをそのまま使ってしまうと、かえって気持ちが伝わりにくくなります。自分の言葉で一文だけでも工夫することで、より心のこもった手紙になります。
こうしたポイントに注意することで、相手に気持ちよく読んでもらえるお礼状になります。
忙しいときでも失礼にならない簡易お礼方法


いくら感謝の気持ちがあっても、日常の忙しさの中ではすぐに手紙を書けないこともあるでしょう。そんなときでも、最低限の礼儀を守って気持ちを伝える方法はいくつかあります。
まずは、メールやLINEなどの即時性のある手段で先にお礼を伝えるのも一つの方法です。ただし、ビジネスシーンや目上の方に対しては、後日改めて手書きや封書でのお礼を送るのが丁寧です。
また、時間が取れない場合でも、一筆箋にひとこと「本当にありがとうございました。とても嬉しかったです」と書くだけでも十分気持ちは伝わります。これにより、「気遣ってくれたんだな」という印象を相手に与えることができます。
さらに、事前にお礼状のテンプレートをいくつか用意しておくことで、忙しいときにもスムーズに対応できるようになります。
時間がなくても誠実に感謝を伝える姿勢が、何よりも大切です。
お礼状に添えるちょっとした贈り物アイデア


お礼状だけでも十分気持ちは伝わりますが、相手との関係や贈り物の内容によっては、ちょっとしたお返しを添えることでさらに心のこもった印象を与えることができます。
例えば、焼き菓子やお茶のセット、季節のタオルなど、気軽に受け取ってもらえる品物が定番です。相手の好みに合わせて選ぶことができれば、さらに印象はアップします。
注意点としては、あまり高額な品を選ばないことです。相手に気を遣わせないよう、あくまでも「感謝の気持ちとしての添え物」というスタンスを大切にしましょう。
また、お礼状の文中で「ささやかではございますが、お礼の品を同封させていただきました」などと一言添えると、自然で丁寧な印象になります。
気負わずに選べる贈り物で、より温かなやりとりを実現しましょう。
お礼状を送るタイミングとマナー


お礼状を送るタイミングは、贈り物を受け取ったその日か遅くとも3日以内が基本的なマナーです。これは、相手に対して迅速に感謝の気持ちを伝えることが、礼儀正しい行動とされているためです。また、お礼状が遅れてしまうと、相手に不快な印象を与える可能性がありますので、早めに対応することが大切です。
ただし、やむを得ない事情で送るのが遅れてしまった場合には、お詫びの言葉を添えると良いでしょう。この際、遅れた理由を細かく説明するのではなく、誠実に謝意を表すことで相手に失礼にならないよう心がけましょう。



お礼状って、いつ送るべきかが大事なんだね!3日以内が理想っていうのはちょっとプレッシャーかも?



確かに早い方が良いけれど、どうしても遅れる場合はお詫びを添えれば問題ないわ。誠意が大切なのよ。
| 状況 | 対応タイミング | 補足対応 |
|---|---|---|
| 贈り物を受け取った直後 | 当日〜翌日中に送る | 手紙・メール・電話など早めに対応 |
| 少し遅れてしまった場合 | 3日以内が目安 | お詫びの言葉を添える |
| かなり日が経ってしまった場合 | 気づいた時点ですぐ対応 | 理由は簡潔に、誠意を込める |
手書きのお礼状とその効果


手書きのお礼状は、送る相手に対して特別な思いを伝える手段として非常に効果的です。手書きであること自体が、手間と時間をかけたことの証明であり、心のこもったメッセージとして相手に伝わりやすいです。パソコンでの印刷物と異なり、一筆一筆に気持ちが込められるため、相手に感謝の気持ちをより深く届けることができます。
ただし、字の美しさよりも、丁寧に書くことが重要です。少々文字が不揃いであっても、丁寧に書かれた手紙であれば相手に誠実さが伝わります。手書きが難しい場合は、パソコンで作成したお礼状に一言メッセージを手書きで添えることも一つの方法です。



手書きのお礼状って効果的だね!でも、字が綺麗じゃないと心配にならないかな?



美しさよりも、丁寧さが大事なのよ。一筆ずつ心を込めて書くことで、相手に伝わるものがあるわ。
お礼状に使うべき便箋や封筒の選び方


お礼状を送る際に使用する便箋や封筒は、相手との関係性や状況に応じて選ぶことが大切です。例えば、目上の方には、白無地の便箋と封筒が最適です。シンプルでフォーマルな印象を与えるため、より礼儀正しい印象を与えることができます。一方、親しい友人や家族には、少しカジュアルでデザイン性のある便箋や封筒を使うことも許容されます。
ただし、あまり派手なデザインや色味は避け、相手や贈り物のシチュエーションに合わせた上品なものを選びましょう。封筒も、サイズが便箋に適したものであること、また封緘(ふうかん)をしっかり行い、丁寧に扱うことが重要です。



便箋や封筒も選ぶべきって、細かい気配りがいるんだね。目上の人にはどんなのがいいの?



白無地が無難ね。シンプルでフォーマルな印象を与えるから、失礼にならない選択よ。
| 相手の関係性 | 推奨される便箋・封筒 | 備考 |
|---|---|---|
| 目上の方・ビジネス相手 | 白無地・縦書き便箋 | よりフォーマルな印象 |
| 親しい友人・家族 | デザイン入りも可 | 上品で落ち着いた柄が望ましい |
| カジュアルな間柄 | はがきやカードでも可 | メッセージ重視 |
句読点を使わない理由と代替方法


お礼状では、伝統的なマナーとして句読点を使わないことが一般的です。これは、句読点が「文を区切る」という意味合いがあり、特にお礼状では「縁を切る」ことを連想させるため、避けられるようになったと言われています。また、句読点は簡略的でカジュアルな印象を与えるため、正式な場面にはふさわしくないと考えられています。
その代わりに、文章の途中で自然に改行を入れたり、適度なスペースを空けることで読みやすさを確保します。改行やスペースを活用することで、文が途切れることなく流れを保ちながら、スムーズに読み進められる工夫が求められます。



句読点を使わない理由が「縁を切る」って考え方、ちょっと面白い!どうやって代わりに整えるの?



改行やスペースを活用するのがコツよ。読みやすくする工夫が、相手への配慮につながるわ。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 句読点を使わない理由 | 縁を切る意味合いがあるため |
| マナー上の理由 | 形式ばった手紙に不適切とされる |
| 代替手段 | 改行・スペース・句読点なしの文体 |
頂き物のお礼状 例文 個人に適した文例集


結婚祝い・出産祝いに対するお礼状の文例
結婚祝いや出産祝いをいただいた場合、お礼状では感謝の気持ちをしっかり伝えるとともに、新しい生活や赤ちゃんの状況に触れると良いでしょう。例えば、出産祝いの場合は、赤ちゃんの名前や健康状態、また贈り物の感想を添えることで、相手に心のこもったお礼を伝えることができます。
拝啓
この度は 私どもの結婚に際し 心のこもったお祝いをいただきまして誠にありがとうございます
おかげさまで 幸せな新生活をスタートさせております
ささやかではございますが 内祝いの品をお送りいたしましたので ご笑納いただければ幸いです
今後とも夫婦ともども 末永いお付き合いをお願い申し上げます
敬具
拝啓
このたびは 私たちの結婚に際し 心のこもったお祝いをいただきまして誠にありがとうございました
おかげさまで 幸せな日々をスタートさせることができました
つきましては ささやかではございますが 内祝いの品をお送りさせていただきましたので どうぞご笑納いただけますと幸いです
これからも二人三脚で支え合いながら歩んでまいりますので 末永く見守っていただければ幸いです
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます
敬具
お中元・お歳暮に対するお礼状の文例
お中元やお歳暮をいただいた際には、感謝の気持ちを伝えるとともに、いただいた品物に対する感想や感謝を具体的に書くことが大切です。相手の気遣いに対して丁寧なお礼を述べることが、今後の良好な関係を築くためのポイントとなります。
拝啓
盛夏の折 心のこもったお中元の品を賜り 誠にありがとうございます
早速家族でいただき 大変美味しく楽しませていただきました
暑さも厳しい日々が続いておりますが どうかご自愛くださいませ
略儀ながら まずはお礼申し上げます
敬具
拝啓
このたびは 結構なお中元(お歳暮)の品を頂戴し 誠にありがとうございました
早速、家族でいただき 大変美味しく楽しませていただきました
日頃からのお心遣いに改めて感謝申し上げます
暑さ(寒さ)も本格化しておりますが どうぞご自愛くださいますようお願い申し上げます
まずは書中にてお礼申し上げます
敬具
快気祝い・お見舞いのお礼状の文例
お見舞いをいただいた際の快気祝いのお礼状では、相手の気遣いに対する感謝と、回復した状況を簡潔に報告することが重要です。相手に対して安心感を与えるとともに、心遣いに対する深い感謝の気持ちを表現しましょう。
拝啓
この度は 私の入院に際しまして 過分なお見舞いを賜り誠にありがとうございました
おかげさまで無事に退院し、現在は自宅で療養を続けております
しばらくはご心配をおかけしましたが 順調に回復しておりますので ご安心くださいませ
まずはお礼まで
敬具
拝啓
この度は 私の療養中に温かいお見舞いのお品を頂戴し 誠にありがとうございました
おかげさまで無事に回復し 現在は少しずつ日常生活に戻りつつあります
温かな励ましのお言葉にも心より感謝いたしております
ささやかではございますが 快気祝いの品をお送りいたしましたので どうぞご笑納くださいませ
略儀ながら まずはお礼まで申し上げます
敬具
香典返しに対するお礼状の文例
香典返しのお礼状では、故人へのご厚志や参列への感謝を丁寧に表現することが大切です。また、法要の報告や相手の健康を祈る言葉を添えることで、より正式な印象を与えられます。
拝啓
先般、亡父(故人名)永眠に際し ご厚志を賜り厚く御礼申し上げます
おかげさまで ◯月◯日に無事に四十九日の法要を済ませました
供養のしるしとして 心ばかりの品をお送りいたしますので、ご受納くださいませ
略儀ながら まずは書中にてお礼申し上げます
敬具
拝啓
この度は 私の療養中に温かいお見舞いのお品を頂戴し 誠にありがとうございました
おかげさまで無事に回復し 現在は少しずつ日常生活に戻りつつあります
温かな励ましのお言葉にも心より感謝いたしております
ささやかではございますが 快気祝いの品をお送りいたしましたので どうぞご笑納くださいませ
略儀ながら まずはお礼まで申し上げます
敬具
入学・入園祝いのお返しに使えるお礼状の文例
入学や入園のお祝いをいただいた際には、子どもの成長や喜びを伝えるとともに、相手への感謝の気持ちを丁寧に伝えましょう。親子で喜んでいる様子を添えると、相手により一層の感謝が伝わります。
拝啓
この度は 娘の入園に際し 心のこもったお祝いを賜り誠にありがとうございます
おかげさまで 娘も元気に園生活を楽しんでおります
ささやかではございますが お礼の品をお送りいたしましたので ご笑納くださいませ
今後とも、親子ともどもよろしくお願い申し上げます
敬具
拝啓
この度は、娘(息子)の入学に際し 温かいお祝いのお言葉と素敵な贈り物をいただき 心より御礼申し上げます
おかげさまで 元気いっぱいに新しい生活を楽しんでおります
ささやかですがお礼の品をお送りいたしましたので どうぞご笑納くださいませ
今後とも親子共々 末永いお付き合いをいただけますと幸いです
まずは書中をもちまして御礼申し上げます
敬具
退職祝いへのお礼状の文例
退職祝いをいただいた際には、これまでの感謝の気持ちと、今後の抱負などを込めたお礼状を送ると良いでしょう。過去のエピソードに触れ、相手との関係を振り返りつつ感謝を表現すると、より心温まるお礼状となります。
拝啓
この度は 私の退職に際しまして
温かいお祝いのお言葉と素晴らしい贈り物をいただき誠にありがとうございます
これまでご指導いただきましたことを胸に 今後も新たな道を精進してまいります
またお会いできる日を楽しみにしております
略儀ながら まずはお礼申し上げます
敬具
拝啓
この度は、私の退職に際しまして、心温まるお祝いと励ましのお言葉を賜り、誠にありがとうございました。
長年のご厚情に支えられ、無事に勤め上げることができましたことを心より感謝申し上げます。
これからもいただいた教えを胸に、新たな生活を楽しんでまいります。
ささやかではございますが、感謝の気持ちを込めた品をお送りいたしましたので、どうぞお納めください。
今後とも変わらぬご交誼をお願い申し上げます。
敬具
遅れてしまったお礼状を書く際の文例
お礼状が遅れてしまった場合には、まず最初に遅れたことへのお詫びをし、その後に感謝の気持ちを伝えるようにしましょう。言い訳をせず、真摯な姿勢でお詫びと感謝を伝えることが重要です。
拝啓
この度は 心のこもったお祝いを賜り誠にありがとうございました
本来ならば 早々にお礼申し上げるべきところ 遅れてしまい誠に申し訳ございません
おかげさまで いただいた品を大変ありがたく活用させていただいております。
何卒 今後とも変わらぬお付き合いをよろしくお願い申し上げます
敬具
拝啓
このたびは 心温まるお祝いを頂戴し誠にありがとうございました
本来であれば早々にお礼を申し上げるべきところ 遅れてしまい申し訳ございません
いただいたお品を大変ありがたく拝受し 日々の生活に大変役立てております
今後とも どうぞ変わらぬお付き合いのほどお願い申し上げます
まずは遅ればせながらお礼申し上げます
敬具
これらの文例をもとに、シーンに合わせてお礼状を作成しましょう。



文例もたくさんあって助かるね!どれも温かみがあって、送った相手に喜んでもらえそうだよ。



その通りね。感謝の気持ちをしっかり伝えれば、良い印象を残せるわよ。
よくある質問(Q&A)
頂き物のお礼状例文集【個人向け】まとめ
- お礼状は贈り物を受け取った日から3日以内に送るのが基本
- 手書きのお礼状は、相手に特別感を伝えるために効果的
- お礼状に使用する便箋や封筒は、相手との関係性に応じて選ぶ
- 句読点は使わず、スペースや改行を利用して読みやすく工夫する
- 結婚祝いや出産祝いでは、感謝の気持ちと新生活の状況を伝える
- お中元・お歳暮では、品物に対する具体的な感想を添えると良い
- 快気祝いでは回復の報告と相手への感謝を述べる
- 香典返しでは法要の報告と相手への感謝を丁寧に伝える
- 入学・入園祝いでは子どもの成長や喜びを添えて感謝を伝える
- お礼状が遅れた場合は、お詫びと感謝の気持ちを真摯に表現する